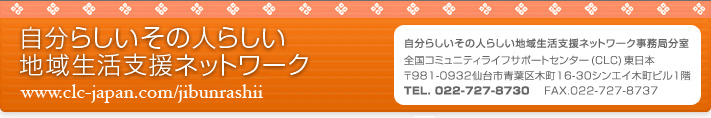 |

|
| [第1回]社会福祉の内と外にあるもの〜その1〜 |
| [第2回]社会福祉の内と外にあるもの〜その2〜 |
| [第3回]寄りそうケアと寄りそえないワーカー |
| [第4回]山で暮らす母ちゃんたちの怒りと社会福祉 |
| [第5回]雪 もう一つの障害 |
| [第6回]出稼ぎに伴う家庭や地域の福祉問題と課題 |
| [第7回]「住民主体の原点を探る」〜人間性の回復を求めて〜 |
| [第8回]熊にも福祉の心を! あるワーカーの叫び |
| [第9回]自分らしいその人らしい地域生活支援! |
 |
私は、東北に生まれ、東北に育ち、東北で福祉活動にたずさわってきた。この東北は、むかし「みちのく」とも言われ、都から遠く離れた野蛮なくにとして蔑まれてきた。しかし、私は、この東北が好きだった。そして、この東北で、人々の福祉の問題にふれながらいろんなことを考えてきた。 1960年から70年代にかけ、日本中が高度成長に浮かれていた頃、東北からは数多くの出稼ぎ者がでていた。東北は、1年のうち半分は雪にうずもれ、その量は想像に絶するものがある。出稼ぎ者がでる頃になると、東北では生活保護を受ける人が多くなる。福祉施設に追い込まれてくる人も増えてくる。ある養護施設では大半が「出稼ぎ家庭の子だ」といったところもでた。園長はいった「出稼ぎさえなければこの子たちは施設にこなくてよかったのに」と訴えた。子どもたちは「どうして俺たちはこんなところによこされたのだ」と泣きながら作文で訴えた。 半年家を留守にする出稼ぎは、さまざまな社会問題を引き起こした。現場工事では事故にあい、無保障のまま帰されるようなケース。出稼ぎ先で夫婦とも行方不明になったり、生別母子家庭が増え、出稼ぎ孤児がでたり、半年留守にされた家庭で子どもたちが親ほしさから非行に走って施設に送りこまれてくるケースなどが増えたりした。 「出稼ぎをしなくてよい世の中にしてほしい」「そして、この子らの人権を守ろう」と訴えた。ところが、経済成長を優先する側の人たちからは「困った人たちを保護するのが社会福祉の役割ではないか。国の農政に口だしするようなことはするナ」とも言われた。口惜しかった。県社協では、1972年から「子どもの人権を守る集会」を各地で開いて社会福祉の立場から、人権の尊さを県民に訴えてきた。「子どもの人権を犯すものを告発する」とまで訴え続けてきた。 |
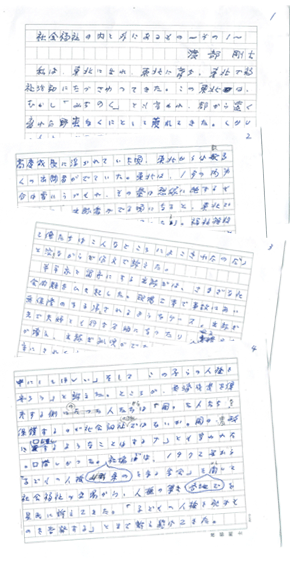 |
 |
最近、北海道に旅をした折、暫くぶりで友人のOさんに逢って話をする機会があった。彼は、北海道名産のカニ料理を前にしながら、延々と北海道の開拓史の話をしてくれた。屯田兵といわれ、未開の地を開発する開拓民の苦難の歴史は、想像を絶するものであった。 彼は最後に、その開拓民の中には山形出身者が非常に多いのに驚いたという話しをしてくれた。私はふと山形のある地域を思い出していた。その地域は、大きな地主が小作人のために行なった救済保護事業で有名な地域。歴代の中央官庁の高官もその地を訪ねたという地域だが、その地域はまた、この北海道に開拓民として沢山の小作人が移住してきた地域でもあった。 私はOさんの話を聞きながら、私たちはいままで、身近な地域での地主の社会事業に目を奪われ、そこに生活できなくて、遥か遠い北海道に渡ってきた名もない、多くの小作人の生活に目もくれず(あるいは他人事として)、いやその関係を切り離して、目先の社会事業家だけを注目してきたきらいがあったのではないか?そう思ったとき、いままで自分がやってきたことはなにか、そら恐ろしい感じがした。 考えてみると、社会福祉施設などでも同じだが、措置されてくる子どもやおとしよりを外から遮断し、収容保護することを主要な役割として馴らされてきた私たちは、保護されてきた人々がかかえる問題を、社会福祉の外にある問題とむすびつけ、社会的問題として提起し、社会的に解決する姿勢に欠けていたのではないだろうか。その結果、社会福祉を社会から切り離し、特定化し、内部では、隔離収容して拘束したり、制裁したりする福祉にしていたのではないだろうか? 広い北海道の高原を旅しながら、そこに苦難の歴史を重ねてきた、同郷の開拓民の人々の足跡に思いを馳せてまた。 |
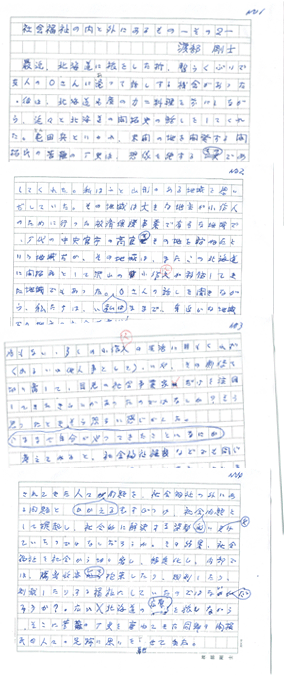 |
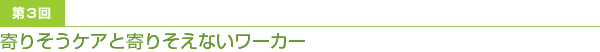 |
最近、よく「寄りそうケア」ということが言われるようになった。「ケア」にとって、利用者がかかえる深い問題に寄りそってケアするということは、「ケアの本質」からいって大変好ましいことである。 しかし、福祉の現場では、利用者がかかえる問題に寄りそえないワーカーも少なくないのではないだろうか。最近、ある福祉施設に伺ったら、そこの「生活相談員」からこんな訴えを聞かされた。「近頃の若い職員は、利用者の言うことばかり聞いて、俺の言うことなど聞いてくれなくなった。俺は国の基準どおりにやっているのに、職員たちは、福祉サービスは利用者主体でやるべきだ、などと言って利用者を甘やかすので、利用者がだんだん図にのって我儘になり困ったものだ」と。 また、ある人は「福祉現場では、利用者に寄りそえばそうほど、利用者の深い問題につき当たるので、ワーカーはそこから逃げているんだ」とも言っている。 そう言えば、私も福祉の施設で、長寿の高齢者でしかも少し認知症をおびた方などとお話をしていると、何を考えているのか判らなくなって、恐ろしくなったときもあったことを思い出した。どうしてよいか判らなくなると、つい規則でしばったり、一方的にこちらの気持ちを押しつけたくなったりした時もあった。「寄りそうケアといって、身体を寄りそうことはできるのが、心を寄りそうのは大変です」と、あるケアワーカーは言った。 私たちは、長い間、国の措置制度に馴らされ、いつの間にか措置基準で人間を視たり、判断したり、接したりしてきたのではないだろうか。だから、利用者がもつ本当の問題に寄りそうことがむずかしくなってきているのではないだろうか。寄りそい、本当の問題にふれることを恐れ、避けて通ってきたのではなかろうか。もしそうだとしたら、大変なことである。 寄りそってみえるもの(・・)から語りあってみる、社会福祉はここからはじまるのかもしれない。 |
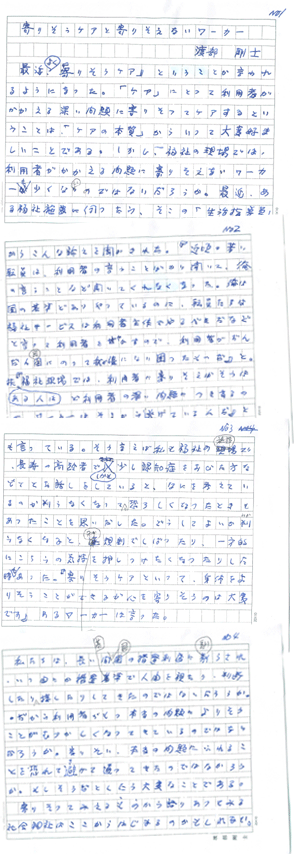 |
 |
東北はどこへ行っても山が多い。そこで暮らしている人もまた多い。東北は春夏秋冬の四季の彩りは格別だが、山の冬は厳しい。
昭和37年、山形で「移動厚生省」が行われた。この事業は、厚生省がよりよい福祉行政を行うための事業の一つであるが、県内では雪が非常に多く高齢化率が進んでいるK町が選ばれ、山の小さな集落が指定されて事業が進められた。 ある日、中央の係官が現地に入るというので、県内の関係者も同行し、大挙現地入りした。現地では、山の集会所にたくさんの人々が集まってきた。座談会が進み、参加者からの質疑や要望の時間となってきたとき、参加者のなかから一人の母親が手を挙げて、こう切り出した。 「あのー、この辺の子どもは、冬は遊ぶところがないため、コタツのなかで火傷する子が多いんです。なんとかならんでしょうか」。これに対し、係官は「児童福祉法ではこうで、法の基準からいくとこうですが――」と長々と説明した。ところが母親は乱れた髪をかきあげ、突然「私たちは、そんなことではないのです。子どもたちの火傷をなくせないかと悩んでいるのです」「法律にないならば、作ってくださいよ」。会場は一瞬シーンとしてしまった。 私は、その母親の切ない叫びと、沈黙のなかに込められた山で暮らす人々の声なき声に圧倒されてしまった。そして、改めて社会福祉とは一体なんだろうと考えさせられた。 人は、誰もが、暮らしのなかで、大変な重い荷物を負いながら生きている。しかも、それは、命にかかるような大きな問題であっても、見過ごされている場合がある。 山村を歩きながら、しみじみ思うことがある。社会福祉は、地域に隠されている人々の暮らしのなかの問題を、もう一度掘り起こしてみることから再構築すべきでないだろうか。雪山で暮らす母ちゃんたちの叫び声を聞きながら思う。 |
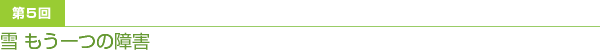 |
東北は、雪国とも言われ、1年の半分は雪につつまれた生活が続く。
雪がコンコン降る この詩は、東北の寒村、山形県山元村の中学教師、無着成恭が学級文集をまとめ世に出した『山びこ学校』の巻頭に載り、各界の方々から注目された。この詩は、炭焼き仕事で学校に来られなかった少年、敏雄の詩である。 雪国の生活は、厳しいものがある。一度油断すると、生命にかかわることが多い。例年、雪による犠牲者があとを絶たない。 昭和48年10月、車いすを使用している障害者が全国から集まり、山形で第6回目の車いす全国集会が開かれた。この集会が地方の小都市で開かれたのは、山形が初めてというから、それまでは全国の大都市だけで行われていたことになる。山形の集会には、全国から400人を超える車いすの障害者が、汽車や飛行機を乗り継いで集まってきた。 この大会では「地域をつくる」というテーマで、3日間真剣な討論が繰り広げられた。 そのなかで、地元実行委員会が「雪国」で生活する障害者の実態を知ってもらおうと、自作の映画をつくって発表した。その題名が『雪もう一つの障害』という映画だった。 雪国では、降り積もった玄関の雪を除雪してもらえないと、外にも出られない。買い物にも役所の手続きにも行けない。道路は、きれいに除雪されないと介添者がいても大変である。 雪という特殊な条件のなかで生きることの厳しさは、そこに生活した者でなければ、計り知れないものがある。「雪もう一つの障害」。 この大会では終始、「誰もが人間らしく、ともに生きられる地域社会」を、誰が、どうやって作るかが問われた。黙っていては何一つ進まない。みんなと手を組まねばと叫ばれた。 |
 |
東北では、雪が降り始める年末になると、家庭や故郷を離れ、半年ほど働きに出る「出稼ぎ」が始まる。
山形県社会福祉協議会が「出稼ぎ問題」に取り組んだ昭和39年当時の資料によると、当時、山形県の総人口は約120万人、そのなかで6万〜7万人の「出稼ぎ者」があったというから大変な数である。 半年、家庭や地域を留守にする「出稼ぎ」は、家庭や地域の暮らしに、さまざまな変化をもたらす。保育所では、出稼ぎ家庭の子どもが多くなってくる。母子寮では、出稼ぎによる母子家庭が増え、養護施設では、出稼ぎ孤児や非行を犯した少年の数が増えてくる。 一方、地域では男手がなく、消防団がなくなったり、緊急の病人への対応も困難になった中山間部も現れた。また、豪雪地帯では、独居老人や障害者、病人世帯の除雪が大きな課題となる。働き手を奪われた出稼ぎ留守家庭では、小さな子どもに学校を休ませ、牛や鳥の世話は年老いた老人が担うといった家庭が、どこにも見られた。 ある小学校の教師の手記に、こんなものがある。「顔を洗わないでくる子ども、散髪や爪切りは勿論、下着は汚れっぱなし、4月になっても冬の綿入れのまま登校する子もあり…」。 山形県社会福祉協議会が「出稼ぎ対策専門委員会」を設置して、「出稼ぎに伴う家庭福祉上の問題と当面の対策」という答申書を出して世に問うたのは、昭和40年だった。この答申書は、議会や国会でも話題となった。そのとき、一部の方から「出稼ぎ問題は、農政の問題だ。社会福祉がなぜ口を出す」という声があった。 出稼ぎ者のなかには、行方不明者も出る。無保証のまま障害者となって変える人も続出する。福祉施設に送り込まれてくる人が増える。 こうしたなかで、いつも社会福祉とは何か。誰が、何をすべきかを問われてきた。 |
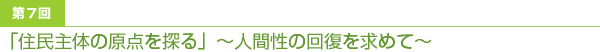 |
国が、社会福祉の構造改革の中で、利用者主体の社会福祉の構築を打ち出してから、随分経つのに、いまだに社会福祉の現場では、国の画一的基準に基づく「保護指導」一点張りの対策から抜け切れないで、多くの問題が発生していることを聞き、これは一体どうしたことだろうかと思う。 振り返ってみると「社会福祉における住民主体の原則」が公の場で話題をよんだのは、昭和37年に出された全国の「社会福祉協議会基本要綱」に「社会福祉協議会は一定の地域社会において、住民が主体となり、(中略)公私関係者の参加協力を得て、住民の福祉を増進する民間の自主的な団体である」と明記されたのを機に、「社会福祉における住民主体論」が、各方面で大きな話題となってきた。そもそも「社会福祉は、憲法で規定された国の責任」で、「住民が主体となるのはおかしいのではないか」といった意見なども出されていた。 実は、この基本要綱が全国から出される2年前、山形で「全国都道府県」の「社協組織指導員」の研究協議会が開かれた。この会議がのちに「山形会議」と言われ、この「住民主体論」に大きな影響を及ぼす結果となったのであるが。 この研究協議会は、山形県の飯豊町(いいでまち)という山間地の小さな農村をメイン会場に、3日間、全国の参加者が現地入りし、現地の人々とともに、現地の実践事例をもとに「今後の方向」を打ち出すために開かれたものだった。 当時、東北の農村は長い戦争の影響で、人々の生活は、荒廃を極めていた。たくさんの人々が戦争で奪われ、多くの遺族や未亡人や戦傷病者が路頭に迷っていた。一方、長い戦争で荒れすさんだ田畑の復旧作業は困難を極めた。そんな中で、娘売り事件や心中事件なども相次いだ。当時は、国がすすめた「生活困窮者緊急生活援護法」による施策だけでは、生きていくことさえ困難な時代だった。 人々は、隣人のために「米」を持ち寄り、「着物」を分かち合い、寒い冬は「毛布」を、「かや」のない人には「かや」を分かち合って、その日の命を支え合ってきた。「たすけあい金庫」や「歳末たすけあい運動」が、民間団体である社会福祉協議会によって盛んに行われたのも、その頃だった。その頃を思い出すと、「社会福祉における住民主体の原則」というのは、暮らしの中における住民の命がけの斗いであったとも言える、のではないだろうか。 |
 |
最近、山間地集落の多い小さな村を訪ねたときのことであるそこに駐在するコミュニティワーカーの話に驚いた。 村の山間地の集落では、熊や猿が増え続け、人口より熊や猿の数が多くなっているところがあり、人々を苦しめているというのである。特に山間地では、とり残された高齢者がその熊や猿に襲われてケガをしたり、命を落としたりする例が増えているというのである。 その高齢者が山を降りてくると、きまって村の社会福祉協議会や福祉施設の介護保険の対象者となってしまう。「これでよいのかな〜」とワーカーは嘆いていた。 ある町社協を訪ねたときのことである。そこは町の中心に立派な保健福祉センターがあり、盛りだくさんの介護保険サービスが実施されていた。そこでのある関係者の話にびっくりした。「介護保険サービスを利用する人が少なくなると、“社協経営”が困難になるので、社会福祉も“経営主義”ですよ」と自慢そうに言っていた。悲しくなった。 最近、私たちは地域を訪ねて「住民主体」のユニークなまちづくり、村づくり運動に驚いている。 そこには、自分たちが住んでいる地域を何とかしよう、誰もが人間らしく、その人らしく暮らせる「地域」にしようといった「熱気」が見られた。既存のしきたりに縛られず、権力におもねらず、自由闊達に創造し、開発し、新しいコミュニティを創りなしていくエネルギーがあった。 あるまちの「まちづくりのリーダー」が言った。「東北には、まだ人と人とのつながりが残っている。共生のコミュニティの源が残っている。古いものから、新しいものを創生していく、まちおこしはそこから始めるべきではないか。社会福祉も同様ではないか」・・・と。 |
 |
自分らしいその人らしい地域生活支援ってなあ−にと、よく聞かれることがある。ふりかえってみると私が、かつて特別養護老人ホームなど様々な施設群の総合施設長にかかわっていたとき、施設運営の基本方針に「利用者主体の原則」をかかげ、実践にとり組んだときがあった。当時、社会福祉は措置中心主義だったから、『措置された者が「自分らしく」「その人らしい生活」をするなどもってのほか』といった考え方が支配的だった。<それは措置機関は勿論、施設現場も教育の現場でも同様であった> 従って、福祉施設の現場では、利用者は決められた以外、自由な行動はゆるされず、食事もお風呂でも自分の意思を表すこともできず、只管、施設の規制に従わざるを得なかった。「利用者主体の原則」はその壁を破って、利用者がひとりひとり「自分らしく」「その人らしく」生活ができることを目指し、環境を改善し、「個」を大事にした支援活動を実践してきた。ところが、内外から、前述したような厳しい意見が寄せられ、一時は職員の中でもぐらついたときがあった。しかし、とうとうその理念を貫いてきた。利用者の生き生きとした顔、輝くような瞳に「利用者主体の原則」を貫いてきたことへのよろこびと誇りを感じたものだった。 その後とり組んだ「施設利用者が地域の中でその人らしい生活ができる支援活動」では、更に大きな抵抗があった。「措置された者をなぜ地域と結びつける?」「施設がなぜ地域生活支援活動にまで手をのばす?」といった意見が沢山寄せられた。私は、今、施設現場を離れて地域を巡り歩きしているが、最近における福祉施設も団体も専門の機関も、なぜかますます狭い「社会福祉」という枠に閉じこもり、社会福祉の対象を特定化し、地域住民の生活と結びつけた支援活動から遠ざかっているように思えて仕方がないが、どうしたものだろうか。 |
Copyright 2007 (c) 自分らしいその人らしい地域生活支援ネットワーク All Right Reserved. |